みんなは、何歳頃、自分の家族が誰で、自分のうちはどこって気がつくの?
わたしの兄は小学校高学年で、気がついたそうです。
わたしは中一でした。
それまで、自分の家がどこなのかわかっていませんでした。
なぜなら、4歳違いの兄とわたしは日中、別の家に預けられていたので。(母が雇っていた)
兄は、怪我をして入院するとき、
「お父さんの仕事は?」
って聞かれて、「大工って答えとったわ」
と言っています。
預けられていた家のおとうさんが左官だったんです。
わたしは、小さい頃は、母を「2階のおばさん」(実家が二階建てだから)、預けられていた家のおかあさんを「おばさん」と、呼んでいたそうです。わたしの頭の中には、母親も父親もなかったのだと思います。
いつか「おばさん」の家の子どもになるのだと信じていました。
母親はしょっちゅう養女に行けと言っていたので(さらに別の家の話だけど)、わたしは「おばさん」の家の子どもになるのだと思っていました。盆も、正月も、長い休みも、その家で過ごしました。自分の親族は知らなくても、おばさんの親族にはいまだに詳しいです。
雇うということが理解できなくて、でも確実な関係がほしくて
「おじさんとおばさんが、じいやとばあやだったらいいのに」
と、小学校低学年の頃、母親に言ったら、
「そんな失礼なこと、言っちゃいけません」
と、ぴしゃりと言われたことを覚えています。
気がついたのは、おばさんに孫が出来たときでした。
おばさんは、小学生の孫たちにしつけをしていました。
「ご飯の後片付けくらいできるでしょう。ちゃんと流しに運びなさい」
雷に打たれたような衝撃でした。
わたしはしつけをされたことがなかったので。
中学生のわたしにはけして言わないことを、おばさんは小さな孫たちに要求していました。
彼女らが、自分の本当の孫だからです。
そして、わたしは、自分がただのお客さんなのだとようやく悟りました。
けしてこの家の子どもになる日はこないのだと。
その日から、誘われても、おばさんの家には泊まらなくなりました。(小5から日中も実家には戻っていたんだけど)
兄が実家に戻ったのは、わたしが小学校低学年のとき、以来ほとんど一緒に過ごしたことはありません。わたしが実家にいついたときには、兄はぐれて友人宅を泊まり歩いていました。
わたしは兄と一緒に過ごした記憶がほとんどありません。
恐ろしい実家の夜を共有したことも。
血がつながっていれば、家族になれるわけではありません。
同じ時間や空間を共有したことのないわたしたちは、いまだに礼儀正しく、他人行儀にふるまいます。嫌いではないけれど、もはや家族にはなれないのです。
義理の姉は兄妹なのに、と不思議がりますが、兄と会うとものすごく緊張します。
親しくない親戚に会う感覚かな。わたしは兄が好きだけど、それでも兄だと思うことは難しいのです。
恐ろしく希薄な家族関係、と兄は表します。
わたしも同じ思いです。
わたしたちは家族と言うものを知らないのです。
幼少期から小学時代までの、自分の家や家族がわからない混乱は、相当根深いものがあります。
安定とか、安心、とか、我儘とか、親に頼るとか、そういう一切を知らないハンデがあります。
大人になっても、親に服を買ってもらうとか、車を買ってもらうとか、よく聞きますが、他の星の話のようです。
親に頼ること、親が何かをしてくれること、それはわたしのフォーマットにはありません。
兄は後継ぎなので、結構資金援助を受けていたみたいですが。
また、兄は後継ぎなので、養子に行け攻撃を受けていません。
わりとあっさりと、自分の実家を受け入れ、中・高でぐれたみたいです。
わたしたちが、育ちの割りに、健康に育てたのは、預けられていた家で、山盛りの愛情を注いでもらったからです。たとえ仕事だったにせよ。
ものすごく感謝しています。兄も、わたしも。あの家が、避難所がなかったら、一体どういうことになっていたでしょうか。
それでも、けしてこの家の子供にはなれないのだと気がついた時の絶望を、わたしは忘れないでしょう。
金烏臨西舎 日ははや西の山におち
胡声催短命 命をきざむ鼓の音
泉路無賓主 迎うる人のなしときく
此夕向誰家 黄泉路へいそぐ今宵かな
大津皇子 直木孝次郎 訳
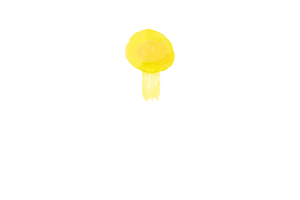

コメント