…わけじゃなかった。
育ての家
私が生まれたとき、おばさんは41歳。後妻でした。娘が一人、高校生。
先妻の息子が三人、皆家を離れて、別の所に暮らしていました。
おじさんは56歳。左官をしていました。
「結婚する時、年を10歳ごまかされた」
というのが、おばさんの口癖。
おばさんは、先妻の息子、特に上の二人とは仲が悪かったです。
長男の長女は知的障害者で、親がその子の面倒を見るのを嫌がったので、施設の休み中、育ての親の家に来ました。年上のお姉さん。だからわたしは養護学級や、同じ教室内の少しずれた生徒とよく遊んでいました。違和感はなかったので。
三男は良く子供連れで里帰りしていて、馴染みました。秋田犬や、カナリアなども一緒にやってきました。
でも私にとっては年下の三男の長男は、セクハラ(小学生のレベルですが)してくるので嫌いでした。心臓病だったので、かなり長滞在していて、居場所が削られていく気がしました。
おばさんの一人娘には良くいじめられました。でも愛情のあるいじめ。
不和のたねはいくらでもあり、時には小爆発していたけれど、命の危険も、空気のように無視されることもなかったなあ。
これが世間一般の、いわゆる家庭かなと思っています。
はじかれたのは、おばさんが孫たちに躾をしていた時。
私は家族ではなくてお客さんなのだと痛感しました。
私を育ててくれる人はもういなくて、自分で自分を育てるしかないことも。
完璧ではなかったことを、少しずつ思い出しながら、やはり育ての親の思い出は美しい。
母がその家を選んでくれたのは、ありがたいことです。
なのに、どうして落ち着いてくれないんだろう?
何が引っかかっているんだろう?
考えても判らないので、感じとれる日を待ちます。
「私らが生き直すことはできない!」
玉音放送を聞きながら、そう叫んだ村長の声を大江健三郎は詩の中で語る。
「四国の森の伝承に、
「自分の木」があった。
谷間で生き死にする者らは、
森に「自分の木」を持つ。
人が死ねば、
魂は 高みに登り、
「自分の木」の根方に着地する。
時がたつと、
魂は 谷間に降りて、
生まれてくる赤んぼうの胸に入る。
「自分の木」の下で、
子供が心から希うと、
年をとった自分が、会いに来てくれる(ことがある)。」
…この伝承の地がどこかは知りませんが、自分の木の下で、私は子供の私と対面中です…。
あんまり役に立たない大人ですが、子供の私は喜んでいてくれているのでしょうか?
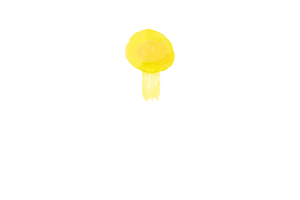

コメント