『ともしびをかかげて』という児童文学がある。わたしは子どもの頃から何十回となくこれを読み返してきた。
ローマ占領時代のブリテン(イングランド)に押し寄せるヴァイキング。撤退し、島から去っていくローマ軍。兵士でもあり、生粋のブリトン人でもある主人公は、家族を殺され、妹をヴァイキングに奪われ、撤退から取り残された状況から生き延びて、アーサー王らしき主の元で、ヴァイキングの襲来を押し戻す。
アーサー王伝説とも絡みながら、主人公はその部下ではあっても、光り輝くその人ではない。主人公の出会う人々や再会した妹は、複雑なタペストリーの中で、きれいごとにならない自分の人生を生きていく。
作者のローズマリー・サトクリフは、小児まひで動かない身体を生きながら、ボタニカルアートと歴史文学に才能を発揮した人だ。
彼女の書く人物には、体温と切り捨てられない何かの傷みが伴っている。闇の中で、たそがれの中で、ともしびを灯す人たちが、子どもの頃わたしはとても好きだった。
今が混とんとしていて、未来もどうしたらいいのかわからない、今が何時で、ここがどこで、周りと自分にどんな関係があるのかわからないという混乱は、ある種の子どもたちのとても馴染んだ世界だと思う。例えば、両親と深く繋がった感覚のない子ども、あちこちに引っ越したり、移動したりが日常である子ども。痛みや感覚過敏について他者に理解されず、自分の感覚をどう取り扱ったらいいかわからない子ども。自閉傾向の強い子ども。
混乱の目で世界を見て、受けとめられることなく、またたった一人の混乱の中に戻っていく。世界はいつも苦痛に満ち、謎めいていて、わけがわからず、何も始まらないままだ。
ファンタジーや歴史小説は、外の世界に混乱があふれても大丈夫なことを、子どもに教えてくれる。外の世界が混乱で埋め尽くされたとしても変化はあり、一歩一歩立ち上がる人がいて、その人たちの足あとが闇の中にともしびとなって、他の人を照らしていく。
「じゃあ、生きていけるのかもしれない」
子どもの頃、わたしは何度もびっくりしながら、世界の枠組みを緩めてきたように思う。
「あんな環境で生きていけて、ぴかぴかの環境じゃなくても喜びがあるんだったら、わたしでも生きていけるのかもしれない」
目の前に見えることだけがすべてではないと、世界の境界が広がっていく。今、目の前にいる100人の人が常識だと語ることが、ここだけのことに過ぎないと、強制力が緩んでいく。構造が柔らかくなる。頭のふたがいつも開いていて、自由に風が吹き込む感じ。
でもそれだけでは足りなかったんだな、と最近、人に心の底から共感してもらう体験をして感じ入った。
わたしと同じ痛み、人と関わることへの恐怖を持つ人が、先を行きながらわたしに言う。輝いて、楽しんで生きている人が、そっと言う。
「わたしの中にも同じ痛みがあるの」
目の奥にその暗がりが見える。けれどもあふれる喜びも共に見える。だから暗がりの底で相手と手を繋ぎ、広くて明るい空を仰ぎ見る。とても身体が暖かい。一人ではないってこういうことなんだ、暖かくなること。流れてきて流れ出すこと。廻ること。
その時初めて、ああこの痛みはなくならないし、なくならなくていいんだなあ、としみじみ腑に落ちた。痛みはあっても歩いていけるし、空は明け、暮れていく。その柔らかさ、しなやかさ、複雑な豊かさ。
誰かが少し先に立って、ともしびをかかげてくれることって、なんてほっとすることなんだろう。
かねがねからわたし自身もスキゾイドの星になりたい、と口癖のように言ってきたけど、つまりはわたしも、傷も痛みも持ちながら(もちろん終わっていったものもあるけれども、人生に深く繋がれば繋がるほど、より深く上がってくる傷もある)、うつろう事象の中で、柔らかな空気や風を感じながら、生きることや人と繋がることの充足を伝えたいんだな、と思う。
わたしにはわたしのともしびがあり、それぞれの人のそれぞれのともしびがあり、自分のともしびをかかげていきることで、世界にはあまたの光や熱が広がっていくんだろう。
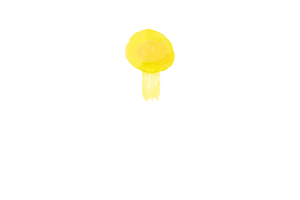

コメント